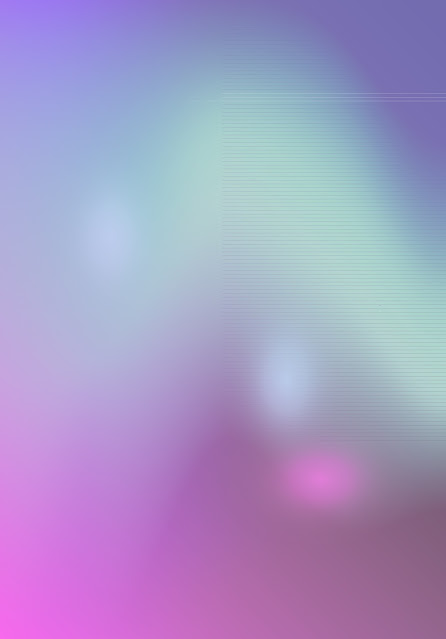やっと逢えたね。
きっとこれは僕だけではなく多くの人々が、この3年間で「風邪」や「インフルエンザ」に罹患しなかったか、あるいは、コロナ以前と比べると激減しているのではないかと思う。
「あ、風邪ひいた」という強い実感は「コロナかもしれない」というフェンスさえ超えれば、こんなにも甘美で、エロティックで、ノスタルジーで、僕は「いやあもう、ほんとに嬉しいよ」と優しい気持ちになることができる。
前回のブログを書いた12月31日、僕は近年最大の激務の1ヶ月を終え、心地よい疲れの中「風邪の予感」と共に大掃除に励んでいた。とは言え発熱もしていなければ喉の痛みもない。なんとなくおでこの奥の方がぐらぐらしているような、温かいような、甘美な気分で過ごしていた。
彼女は「久しぶり、やっと逢えたね。」そんな映画の台詞のような甘い言葉を僕に囁いているような気がしていた。
野口晴哉の「風の効用」は名著であると思っているし、僕の風邪に対する見解はこの本に書いてある。コロナ以前は激務が続き、酷い疲れの後はよく風邪をひいていた。最近あまりにもひかないので忘れていたけれど、もしかしたら、人よりもよくひく方なのかもしれない。
僕はコロナ以前、風邪で仕事に穴を空けた事は美容師になってからの20年間、ノロウイルスの時を除いて殆どない。
要するに、風邪が好きなのである。風邪との合一感は凄い。かなり上手くいったセックスをはるかに凌ぐものがある。なにせ、具体的に、一体となるのだから。
3年間があっという間だということは、どなたでもご存知だろう。年齢で言えば20歳になった子が23歳になるまでの間だ。気がつかない人には、気がつかない程度の期間だ。
12月31日に突如、3年ぶりの再会を果たした風邪は、しばらく僕の中にいて見守ってくれていた。
お店の大掃除や事務仕事を遅くまでこなす大晦日。地元に帰り家族で祝う元旦。沖縄旅行。1年ぶりの再会でワインを飲み交わし楽しいひと時を過ごしたmuiでの時間。海にテーマパークに、久しぶりに娘と精一杯遊ぶ時間。
彼女は家事でもしているか、自分の仕事でもしているかのように、同居しながら静かに見守っていた。そして、風邪は、「お疲れ様。頑張ったね」といって、僕に抱きついてきた。それが1月6日、帰りのなぎさまち行きのフェリーで眠りについていた15時の頃。
自宅に帰り、計測した体温は37.3℃という、スムースとしか言いようがない数値。3年ぶりの抱き心地。
「コロナの間、君、どうしてたの?」
「自分でもわからないわ」
「久しぶりじゃん」
「嬉しい?」
「ああ、もちろんさ」
未嗅覚をチェックする必要もなかった。抱き心地を記憶できない人物は悲しい人物である。しかし、頭の中で緊急会議は開かれた。
翌日からの予約がパンパンに入っていたからである。
発熱は37.8℃まで上がり、37.2℃との間をゆっくり移動していた。僕の風邪は、経験則で殆ど過労と結びついている。風邪は、蓄積された過労を解放し、過労を過労と感じないままに積み上げられた身体の歪みを、一挙にほぐし、解放する。
すぐに近所のかかりつけの内科に電話して行った。「絶対にない」と思っていたが、もし陽性の判断があったら向こう1週間に予約の入っている30人全員に謝罪の連絡を入れて、家族に迷惑がかからないようにビジネスホテルで過ごすことにしようかな。そんな事を考えていたら、直に陰性証明書が届いた。僕は先生から風邪薬を貰い、帰り道にコンビニで買った温かいスープを飲み、念の為翌日に予約の入っていた方々に謝罪とキャンセルの連絡を入れ、17時にはベッドに入り、そのまま14時間も眠り続けた。それは飛び込んで行くような感覚。
彼女は夢の中で僕を柔らかく抱きかかえ、僕の顔をさすりながら、時折、自分の唇に自分の指を当て、その指を僕の唇に当てながら会話を始めた。
「ねえ、このまま誰もいない湖に2人で行かない?」
「でも、身体が重たくて動けないよ」
「若い頃は、このぐらいの熱だったら、どこにでも連れて行ってくれたでしょう?」
「そうだね。色々な間違いを犯していたよ」
「どういう事?」
「あれもこれも、ただ疲れていただけだったんだ。全部に理由があると思っていたのに」
「そう。かわいそうに。歳をとったのね」
「そうだよ。かわいそうでしょ。笑」
「あなたが好きよ」
「例えばどこが?」
「負けたがってるから」
「・・・・・。」
「私と逢うときだけはね。」
「・・・・・。」
「最初に会ったときのこと、覚えてる?」
「ああ。」
「あなたのお母様は、あなたにたくさん布団をかけてくれた」
「ああ」
「忙しいお父様は、あなたが熱を出してることも知らなかった」
「ああ。そうだ」
「あなたは、まだ好きな女の子さえいなかったわね」
「ああ」
「あたしの姿はいつ決めたの?」
「わからない。多分、映画館の中だと思う」
「そう。あたしね、あなたに初めて会った時に思ったの」
「何を?」
「芸術って、とても不自然なものだって」
「そうか。笑」
「あなたが、それを愛し始めてるって」
「へえ。笑」
「ねえ、今、あなたがしてることは何?」
「髪を切っている」
「今、負けたい?」
「ああ」
「もっと負けて。すごくすごく素敵」